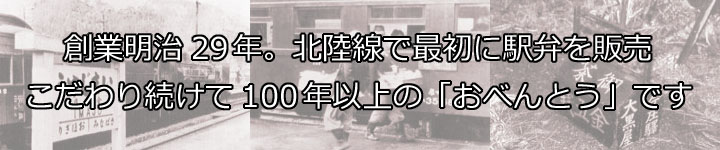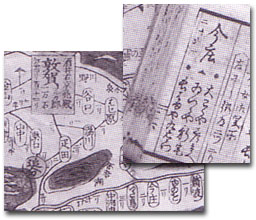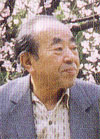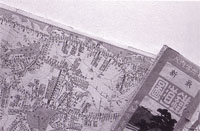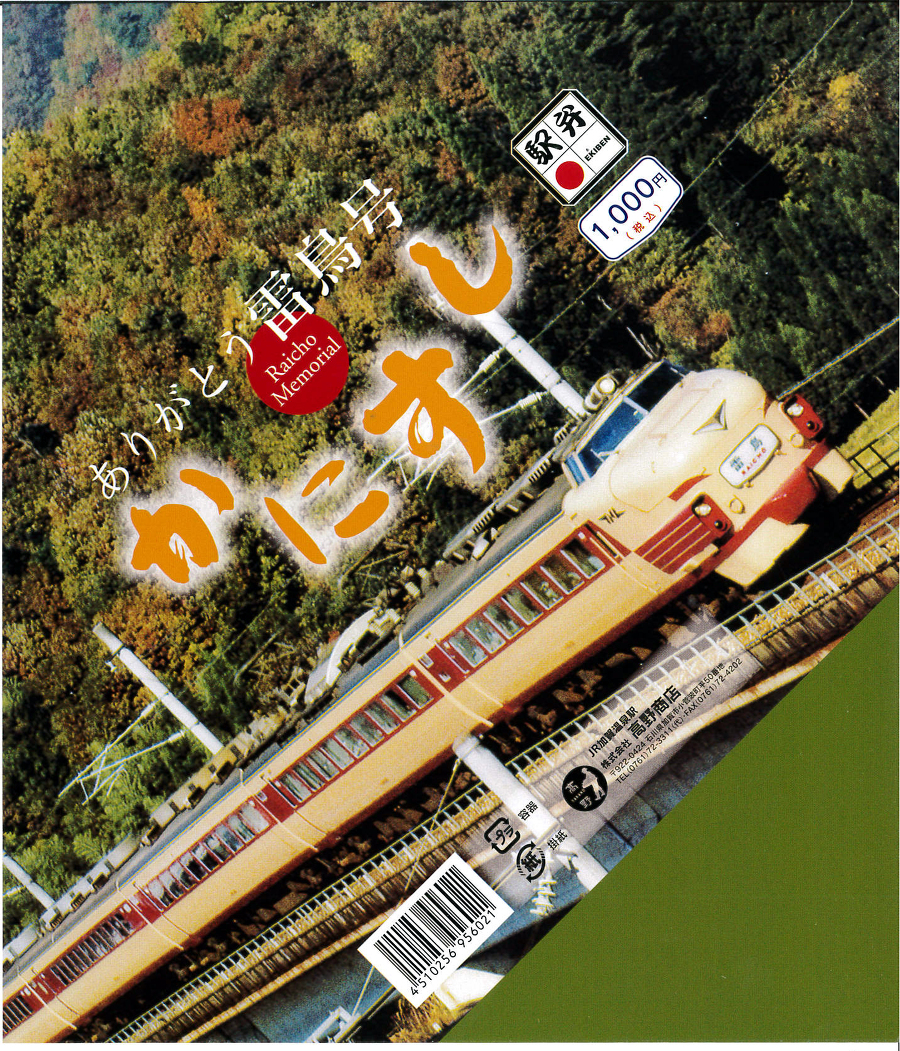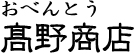
|
�k���̊C�̍K�A�R�̍K���ӂ�Ɏg�������������w��
�@���쏤�X�́A100�N�ȏ�̊Ԃ�����葱�����w�ق₨�ٓ��� �@�S���̊F�l�ւ��͂����Ă��܂��B |
������Ѝ��쏤�X �ΐ쌧����s�����g����50 Tel 0761-72-3311
|

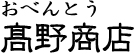
|
������Ѝ��쏤�X �ΐ쌧����s�����g����50 Tel 0761-72-3311 |
|
�k���̊C�̍K�A�R�̍K���ӂ�Ɏg�������������w��
�@���쏤�X�́A100�N�ȏ�̊Ԃ�����葱�����w�ق₨�ٓ���
�@�S���̊F�l�ւ��͂����Ă��܂��B |
|
��
|
|
|
|�@HOME�@
|�@�j���[�X�ꗗ�@
|�@���쏤�X�̉w�ف@
|�@���쏤�X�̗��j�@
|
|�@�w�قp���`�@
|�@�u���O �ٓ������L�@
|�@��Јē��@
|�@�T�C�g�}�b�v�@
|
������Ѝ��쏤�X �ΐ쌧����s�����g����50
Tel 0761-72-3311�@Fax 0761-72-4202 |

Copyright © TAKANO-SHOTEN / obentou-takano.com Inc. All Rights Reserved.